ザワザワと木の葉と木の葉の擦れ合う音は、まるで森の中の平穏を告げる声のようだ。
狐族が生活を過ごす森から少し離れた、背の高い木々の集まる所にゼロスは一人立っていた。
普通の狐族より垂れ下がった特徴的な可愛らしい耳、水が流れるようになだらかな銀色の髪とちょこんと姿をのぞかせる尻尾。
傍から見れば美しいそれらも、ゼロスにとってはコンプレックスでしかなかった。
なぜ自分だけが兄二人とは違うのだろうと今でも悩んでいるが、悩んだところで生まれもっての体の特徴は変わることはない。
ゼロスはよく分かっているつもりだった。
それでも一人きりでいる時はどうしても悩みとなってのしかかってきて、ゼロスを暗い気持ちにさせる。
(ワンス兄さんの様に気楽だったらどれだけ楽だろう)
くい、と顎を上げて雲が気持ち良さそうに泳いでいく青空の海を見上げた。
ため息を遠い雲に吐きかけてみる。
雲は相も変わらず同じペースで流れて行く。
ゼロスはもう一度深く溜め息をつくと、茶色い木の幹にもたれ掛かるようにして座りこんだ。
ちょうどその時、ガサガサと、騒がしく足元に生い茂っている草を踏み分ける音がゼロスの垂れた耳に届いた。
「ごめ〜ん。ゼロス。遅くなっちゃった」
その後に続くのは気楽な、本当に悪いと思っているのかどうか分からないワンスの声。
ゼロスには声を聞くまでもなく、向かって来ているのがワンスだと分かっていた。
待ち合わせをしていた、ということもあった。
しかし、それが判断の材料ではない。
こんなに無神経に草の音を奏でるのは狐族ではワンスくらいしかいないのだ。
あえてそのことには触れず、ゼロスは立ち上がって服についた汚れを片手で払いながら答える。
「別に気にしてないよ」
そして、次はさすがに不安げに尋ねる。
「で、誰にもここにぼく達が来てることは気付かれてないよね?」
「大丈夫だよ! 絶対に気付いてないって。も〜、ゼロスは心配し過ぎだって!」
くしゃくしゃに跳ねたブロンドの髪を揺らしながらワンスは屈託なく笑う。
「まぁいいや。じゃあ始めよう」
ワンスに合わしていたらキリがないと思ったのだろう。
ゼロスは杖を取り出した。
「よ〜し、始めよう! トゥース兄ちゃんにこればっかりはバレたらマズいからね!」
ワンスも手を大袈裟に振り上げ、早速準備に取り掛かろうとした───
───その時、横に並んだワンスとゼロスの頭の上に何か、温かいものがぽす、と乗っかかってきた。
そして、同時に呆れ切った言葉が降ってくる。
「へぇ、オレにバレたらマズいことねぇ。一体今日はどんなイタズラをするつもりだ? しかも、ゼロスまで連れて」
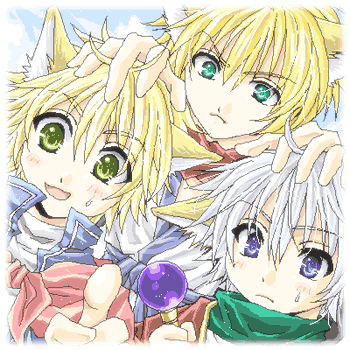
あ〜あ、と小さく漏らすゼロス。
顔からサーっと血の気が引いていくのを生まれて初めて感じるワンス。
数秒、空気が凍結したような気がした。
だからと言ってゼロスが魔法で凍らせたわけではない。
頭の上に乗った温かい何かは、二人の兄、トゥースの手だったのだ。
三人の父であるフォースからもらった真紅のスカーフがわずかに揺れている。
相当素早く動いたのだろう。
しかし、足音らしい足音もしなければ、気配すら感じられなかった。
(ワンス兄さんとは大違いだね)
ゼロスは心の底から思った。
そして、ワンスが勝手に口を滑らしてしまう前に口を開き出す。
「トゥース兄さん。別にワンス兄さんはともかく、ぼくはイタズラのためにここに来たんじゃないよ」
「そうなのか? じゃあ何してるんだ?」
よほどワンスは家を出る前に怪しい挙動をしたらしい。
初めからイタズラだと決めつけていたトゥースは目をしばたたたかせて、意外そうな口調で再び尋ねた。
「ワンス兄さんがこっそりと隠れて魔法が使えるようになって、トゥース兄さんをびっくりさせたかったんだってさ」
あたかも自分は無理矢理付き合わされているかのような体を装い、ゼロスは言う。
「そうなのか? ワンス?」
「あ……う、うん」
感心から声に喜色を混じらせるトゥースに、ワンスは戸惑いながらも何とか答える。
「そうか、悪かったな。じゃあ、練習の邪魔にならないようにオレは帰っておく。父さんや母さんには内緒にしといてやるよ」
トゥースはそう言って二人の頭をガシガシと撫でると、満足そうに手を離した。
「じゃ、いつかオレを驚かせてくれよ! 待ってるぜ」
すると、再び音もなく森の中を素早く駆けて行った。
姿が見えなくなるまで、二人はトゥースの背を目で追う。
そして、トゥースのブライトゴールドの髪が森の明るい緑に溶け込むのにそう時間はかからなかった。
「はぁぁぁぁ〜〜。助かった〜〜。けど良かったのかな?」
今まで呼吸を止めていたかのようにワンスは幹にもたれ掛かって息を吐き出した。
「別に嘘はついてないよ」
ゼロスがその言葉にさらりと答える。
「だよね? トゥース兄ちゃんを驚かすために魔法の勉強してるんだから」
その言葉に、ワンスはすぐにいつもの調子に返り咲いて、ひょいと一跳ね。
尻尾も一緒に上下に揺れる。
「早くやろう。トゥース兄さんの誕生日に大きな雪の結晶を作るんでしょ? って言っても、誕生日はまだまだ先の話だけど」
「何でも早くから始めた方がいいよ! それに───」
「それに?」
「ゼロスの好きな魔法の練習だから、ゼロスも楽しそうだしね!」
ぽかん、とゼロスは口を空けた。
実の所、最初から不思議でしょうがなかったのだ。
なぜ魔法が苦手なワンスがわざわざ氷の魔法を使ってトゥースの誕生日に何かをしてやりたいなんて言い出すのか。
「それに、魔法のことが分かったらゼロスと話すこともたくさんになるし」
恥ずかしそうにピンと立った耳をかいてワンスは笑う。
何も考えてない様に見えて、実はゼロスのことを考えていた。
そう思うと、ゼロスは何か申し訳ないような、恥ずかしいような気持ちで胸が満たされてゆくのを感じる。
つまりは、うれしいのだ。
はにかんで、うつむくゼロス。
「あれ? どうしたのゼロス? 元気ないよ?」
しかし、ワンスはそんなゼロスの気持ちなど気にせず、いや、気がつかずに声をかける。
さっきまでの気遣いはどこへやら。
ゼロスは呆れて頭に手を乗せる。
ふぅ、と溜め息。
今日だけで何度目だろう。
「ワンス兄さんってよく考えてるのか何も考えてないのか分かりにくいね」
でも、今回のは嫌じゃなかった。
横目でちらりとワンスを見つめる。
「なんか、バカにしてない?」
不満げにぼやくワンス。
「むしろ、褒めてるんだよ」
ワンスに背を向けながら小さく呟いた。
その時、ゼロスは僅かに、でも確かに笑っていた。
本当に〜?、と森の中で嬉しそうに尋ねる狐族の少年の声が響き渡り、風に乗った。
木々を飛び移ってさえずる鳥達の合唱に、二人の草むらをかきわける小さな音と葉っぱの囁き。
太陽の下で、温かな森の息吹はみんなを優しく色付ける。
ワンスのいつもの笑顔も、もちろんゼロスの時折覗かせる微笑みも、みんなそろって綺麗に彩られていた。
ここだけのお話。
寒い寒い冬の、トゥースの誕生日。
クライン家では、綺麗な綺麗な赤い雪の結晶が、溶けることなくきらきらと輝いていたそうな。